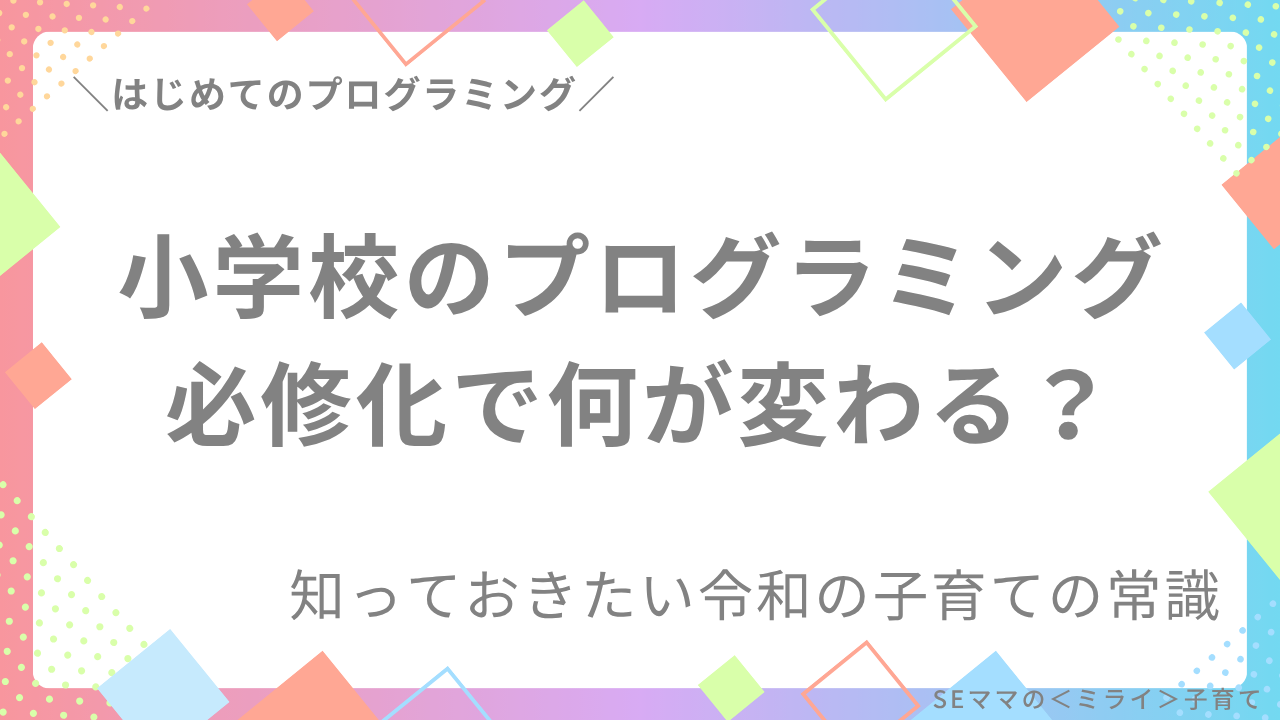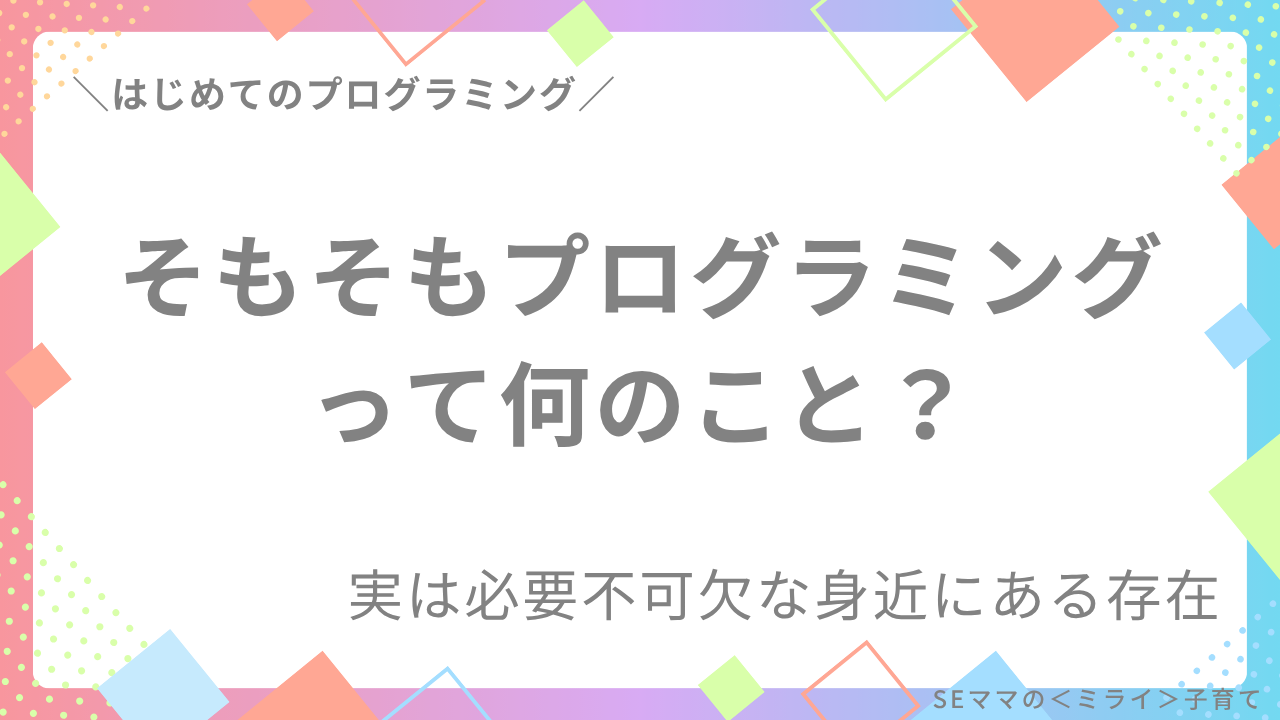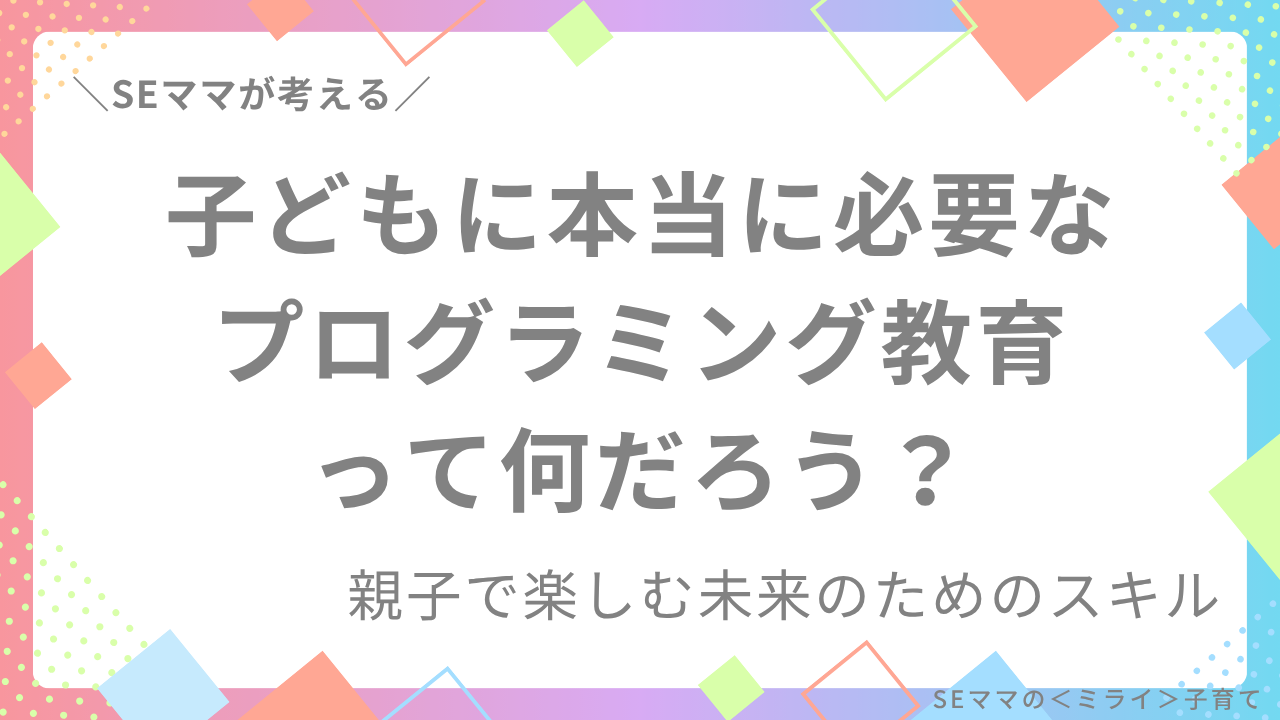「学校でもプログラミング教育が始まったって聞いたけど、うちの子は大丈夫?」
「何をやっているのかよくわからない…」
「家で何をフォローしてあげればいいのか全然分からない」
こんな不安を感じている保護者の方、実はあなただけではありません。
2020年から始まった小学校でのプログラミング教育必修化は、令和時代の子育てにおける最も大きな変化のひとつです。
しかし、勘違いされがちですが、小学校でのプログラミング教育は難しいコードを書くような職業訓練ではありません。
小学校のプログラミング教育は、今の子供たちにとって、未来に必要不可欠なスキルの学習なのです。
この記事では、プログラミング教育必修化で実際に何が変わったのか、そして令和の子育てに知っておきたいことを、ママ目線でお伝えします。
この記事を書いた人
そもそも、なぜプログラミングが必修化されたの?
「コーディング」を覚えることが目的ではない!
多くの保護者が誤解していることの一つが、「小学校でプログラミング言語を覚えさせるんでしょ?」という認識です。
実際は全く違います。
文部科学省が目指しているのは「身近なコンピューターに気づき、理解し、活用できるようにすること」「プログラミング的思考の育成」「コンピューターを活かそうと学びに向かう力」なのです。
特に注目される「プログラミング的思考」というのは、このような考える力のことを目指しています。
- 物事を順序立てて考える力
- 問題を分解して整理する力
- 論理的に筋道を立てて考える力
つまり、日常生活でも使える「考える力」を育てることが本当の目的なのです。
デジタル社会を生きる子どもたちのために
令和の時代、お子さんが大人になる頃には、今よりもさらにデジタル化が進んでいることは間違いありません。
その時に必要なのは、コンピュータがどのように動いているかを理解し、上手に活用できる力なのです。
Society 5.0時代を生き抜くため
日本が目指す未来の姿である、Society 5.0とは、AIやIoTなど先進的テクノロジーがが社会の隅々まで浸透し活用される、いわば超スマート社会のこと。
この社会では、「デジタルを使いこなせる」ことが基本的な生活スキルになります。
私たちが電卓を当たり前に使うように、今の子どもたちはAIやプログラミングを当たり前に使う世代になるとされているのです。
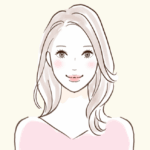
プログラミング教育は未来に必要不可欠となるスキルの一つです。
実際の授業って、どんなことをしているの?
「プログラミング」という教科はない!
驚かれるかもしれませんが、時間割に「プログラミング」という教科は存在しません。
- 算数の時間:図形の性質を調べるために、コンピュータで正多角形を描く
- 理科の時間:電気の働きを学ぶために、LEDを点滅させるプログラムを作る
- 総合的な学習の時間:地域の魅力を伝える簡単なゲームを作る
このように、既存の教科の中で自然に取り入れられているのです。
使う道具も子どもに優しい
「難しいプログラミング言語を覚えるの?」という心配も不要です。
小学校では、ビジュアルプログラミングといったアイコンやマークを並べて操作するプログラミングツールが使われています。
- Scratch(スクラッチ):ブロックを組み合わせるだけでプログラムが作れる
- viscuit(ビスケット):絵を描いて動かすことができる
- ロボットプログラミング:実際に動くロボットを操作できる
文字を打つ必要がほとんどないので、低学年からでも楽しく学べます。
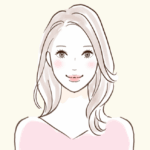
小さなお子さんでも簡単に操作できるようなプログラミング教材がたくさん開発されています。
プログラミング教育の新常識
新常識1:「プログラミングは習い事」として捉える
ピアノや水泳と同じように、プログラミングも継続的な習い事として考えるのが令和の常識です。
新常識2:早い子は年長からプログラミング教育を取り入れている
プログラミング教室は年長からのコースも増えています。
早い子は年長からプログラミング教育を受けているのです。
新常識3:「プログラミング的思考」を日常に
- 料理の手順を子どもと一緒に整理する
- 片付けの手順をルール化する
- ゲームの攻略法を論理的に考えてもらう
新常識4:親も一緒に学ぶ姿勢
子どもの質問に答えられるよう、親も基本的な知識が必要な時代かもしれません。
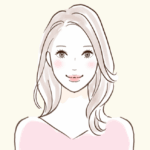
私も日々勉強ばかりです。子供と一緒に新しい発見を楽しんでいます。
家庭学習の始め方
【年長〜小学2年生】
推奨: ビジュアルプログラミング(Scratch Jr.など)
時間: 週1-2回、1回30分
目標: 「順序立てて考える」習慣づけ
【小学3年生〜4年生】
推奨: Scratch、マインクラフトプログラミング
時間: 週2-3回、1回45分
目標: 条件分岐、繰り返し処理の理解
【小学5年生〜6年生】
推奨: テキストプログラミング(Python入門)
時間: 週3-4回、1回60分
目標: 実用的なプログラムの作成
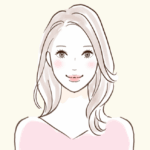
いきなり難しいことに挑戦するよりも、楽しく学べるよう学習を進めていきましょう。
令和時代に求められる「AIと共存する力」
AIにできないことを伸ばす
- 創造性: オリジナルのアイデアを形にする力
- 共感力: 人の気持ちを理解し、寄り添う力
- 問題発見力: まだ誰も気づいていない課題を見つける力
AIを使いこなす力
倫理観: AIを正しく使う判断力
プロンプト作成能力: AIに適切な指示を出す力
情報選別能力: AIの出力の正確性を判断する力
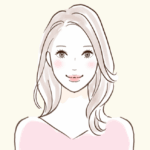
AIの時代に子供にとって必要な教育は何か、私も日々考えさせられるばかりです。
まとめ:令和の子育て知っておくべき3つのポイント
1. プログラミング教育の必修化は「スタートライン」
学校教育は最低限のベース。
本当の力をつけるには家庭での継続学習が不可欠とも言えます。
2. プログラミング教育を始める時期が大切
デジタル格差は学力格差に直結するとも言われている時代です。
プログラミング教育をいつ始めるかが大切です。
3. 親も子供と一緒にプログラミング学習を!
プログラミング教育は、親も一緒に新しい時代の学びに向き合うことが必要でしょう。
子供と一緒に、ぜひ学びの幅を広げてみてくださいね。
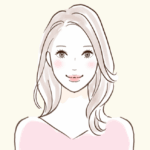
「もっと早く始めればよかった!」と後悔しないためにも、少しでも気になったらプログラミング教育を始めてみてくださいね。お子さんのミライのスキルの第一歩です。