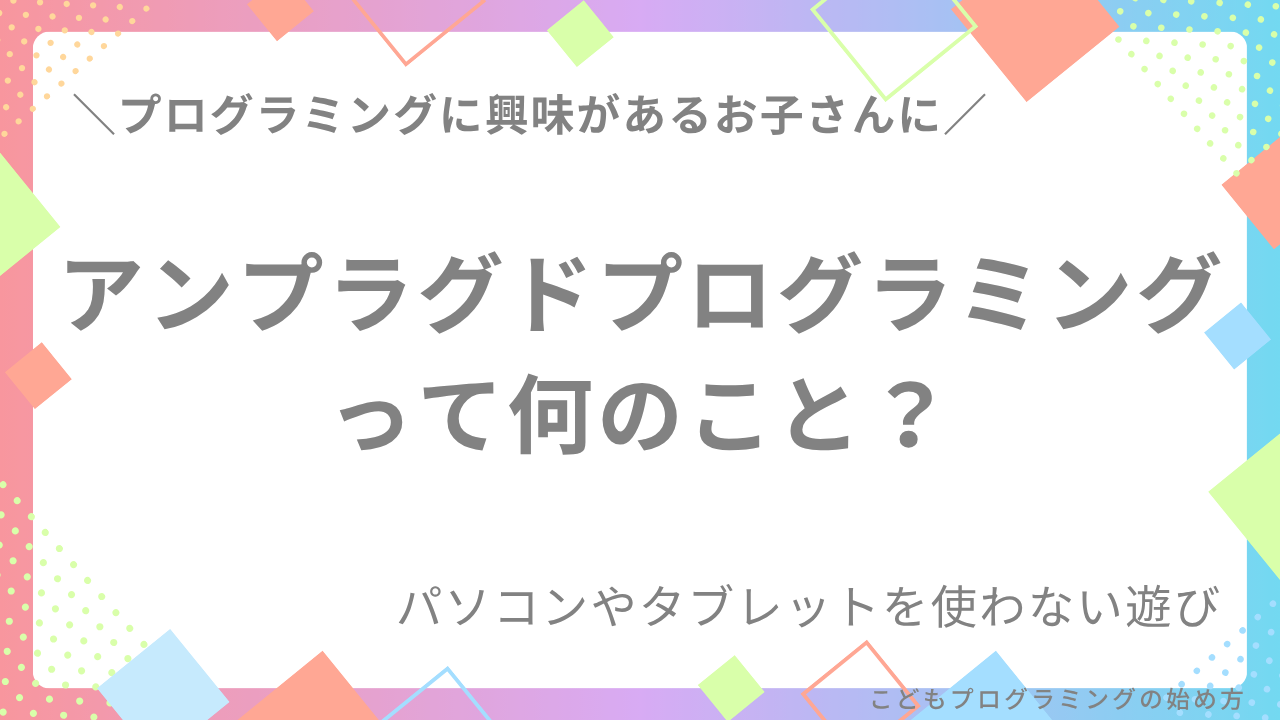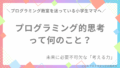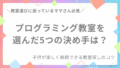「プログラミング教室に通わせたいけれど、まずは家で何かできることはないかな?」
「プログラミング的思考はパソコンがないと育てられない?」
「まだあまりタブレットやパソコンを使わせたくない」
そんなママたちに朗報です!
実は、特別な機材がなくても、おうちにあるものや身近な遊びを使って、楽しくプログラミング的思考を育てることができるんです。
今回は、実際に試してみた「アンプラグドプログラミング」の遊びを5つご紹介します。
どれも簡単で、親子の絆も深まる素敵な時間になりますよ!
この記事を書いた人
「アンプラグドプログラミング」って何?
パソコンを使わないプログラミング学習
アンプラグドプログラミングとは、パソコンなどのICT機器を使用せずに、プログラミングの考え方やコンピュータの仕組みを学ぶための学習方法です。
主にカードや本、ときにはおもちゃなどを使って学習を進めていきます。
パソコンなどのコンピュータを使わない学習方法なので、小さなお子さんでも気軽に取り組むことができます。
なぜアンプラグドが効果的なの?
- 年齢を選ばない:3歳頃から楽しめる
- 親子で一緒に:コミュニケーションが生まれる
- 体験型学習:体を動かしながら理解できる
- 費用がかからない:身近なもので始められる
アンプラグドプログラミングは、プログラミング教育の前段階として基本的な考え方を身につけるのにぴったりです。
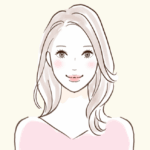
タブレットやパソコンをまだ使わせたくないな…と感じているママさんにもおすすめです。
遊び1:「人間ロボットゲーム」で順序立てて考える力を育てる
遊び方
- 「ロボット役」と「プログラマー役」を決める
- ロボット役:指示通りにしか動けない
- プログラマー役:ロボット役に指示を出す
- 簡単なお題を設定
- 「おもちゃ箱から車のおもちゃを取る」
- 「冷蔵庫から牛乳を取って、コップに注ぐ」
- 具体的な指示を考える
- プログラマー役が「3歩前に歩いて」「右を向いて」「しゃがんで」など、細かく指示を出す
子供の考える力
- 分解思考:大きなタスクを小さな動作に分解
- 順序立て:効率的な手順を考える
- デバッグ:うまくいかない時の修正方法を学ぶ
遊び2:「お料理レシピゲーム」で手順を論理的に考える
遊び方
- 簡単な料理を選ぶ
- おにぎり、サンドイッチ、フルーツサラダなど
- 手順を順番に書き出す
- 紙に1番から順番に手順を書く
- 子どもと一緒に「次は何をする?」と考える
- 実際に作ってみる
- 書いた手順通りに料理を作る
- うまくいかない部分があれば修正する
子供の考える力
- 順序関係:前後関係を正しく理解する
- 条件分岐:「もし塩気が足りなければ、塩を少し足す」など
- シミュレーション:こうすればどうなるかをイメージする
発展版
- タイマーゲーム:制限時間内に完成させる
- 材料制限:決められた材料だけで作る
- 味見判定:味見をして調整する手順を追加
遊び3:「宝探し迷路」で問題解決力を鍛える
遊び方
- 家の中に迷路コースを作る
- マスキングテープで床に道筋を作る
- 椅子や本などで障害物を置く
- 指示カードを準備
- 「→(右に1歩)」「↑(前に1歩)」「×(待機)」などのカード
- 宝探しゲーム
- スタートからゴール(宝物)まで、カードを並べて道順を考える
- 実際に歩いてみて、正しくゴールできるかチェック
子供の考える力
パソコンもタブレットも使わずにプログラミングをとても簡単に学習できます
- 空間認識能力:方向感覚と位置関係の理解
- 論理的思考:効率的なルートを考える
- 試行錯誤:間違いを修正する経験
アレンジアイデア
- 2人プレー:友達と一緒に最短ルートを競争
- 逆さま迷路:ゴールからスタートへ戻る道筋を考える
- 時間制限:制限時間内にクリアする
遊び4:「お片付けアルゴリズム」で効率化を学ぶ
遊び方
- 散らかった部屋の写真を撮る
- ビフォー写真として記録
- お片付けの手順を一緒に考える
- 「まず大きなものから」「次に小さなもの」
- 「本は本棚、服は洋服ダンス」など分類ルールを決める
- 効率的な順番を話し合う
- 「なぜその順番がいいと思う?」
- 「もっと早い方法はないかな?」
子供の考える力
- 分類思考:カテゴリー分けの能力
- 優先順位:重要度や効率を考える力
- 最適化:より良い方法を常に考える習慣
遊び5:「絵本ストーリー作り」で創造性と論理性を育む
遊び方
- キャラクターと設定を決める
- 主人公、場所、目標を設定
- 「うさぎさんが森でどんぐりを探す話」など
- ストーリーを順序立てて考える
- 起:うさぎさんがお腹を空かせている
- 承:どんぐりを探しに森へ出かける
- 転:途中で困った問題が起きる
- 結:問題を解決してどんぐりを見つける
- 「もしも」の分岐を考える
- 「雨が降ったらどうする?」
- 「どんぐりがなかったらどうする?」
子供の考える力
- 構造化思考:物事を整理して組み立てる力
- 条件分岐:場合分けして考える能力
- 創造性:自由な発想と論理的思考の両立
発展版
- 絵本作り:実際に絵と文章で本を作成
- 演劇ごっこ:ストーリーを演じてみる
- 続編作り:「その後どうなった?」を考える
おうちプログラミング教育を成功させるコツ
1. 「正解」を求めすぎない
大切なのは、子どもの自由な発想を認めてあげることです。
どうすれば上手くいくかの試行錯誤を楽しみましょう。
2. 失敗を歓迎する
一度ですべてが上手くできる必要はありません。
「あれ?うまくいかなかったね。どうしてかな?」と一緒に原因を考える時間を楽しみましょう。
3. 「なぜ?」「どうして?」を合言葉に
なんとなく上手くいったよりも、理由を聞いて上手くできた過程を褒めてあげましょう。
できた結果も大切ですが、考えている過程も重要です。
4. 段階的にレベルアップ
最初は2、3ステップで成功するような簡単なものから始めましょう。
いきなり難しいことに挑戦すると、子供が嫌になってしまう可能性があるので注意しましょう。
5. 褒めるポイントを明確に
褒めるときは、具体的に褒めるのがポイントです。
「ゴールできたね、すごいね!」より「順番を工夫したのがすごいね!」と具体的に褒めましょう。
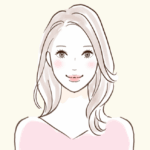
あくまで遊びは楽しいことが一番です。
遊びを通じて見えてくる成長のサイン
こんな変化があったら成長のサイン!
日常生活で
- 朝の準備を自分で順序立てて行うようになる
- 「こうしたら早いかも」と効率を考えるようになる
- 問題が起きても冷静に対処法を考える
学習面で
- 宿題を小分けにして取り組むようになる
- 間違いを見つけて自分で修正する
- 「なぜ?」と理由を考える習慣がつく
友達関係で
- トラブルを論理的に説明できる
- 相手の立場に立って考えられる
- 協力して問題解決に取り組める
まとめ:特別な道具は不要!愛情と工夫があれば十分
アクティビティ・絵本・ボードゲーム・おもちゃなど、学習方法の幅広さもアンプラグドの魅力です。
今回ご紹介した5つの遊びは、どれも特別な準備や高価な教材は必要ありません。
- 親子で一緒に考える時間
- 子どもの「やってみたい!」を大切にする気持ち
- 失敗も含めて楽しむ雰囲気作り
これらが大切です。
この遊びを通して、親子やお友達とのコミュニケーションも深めていきましょう。
忙しい毎日の中で、子供と一緒に遊ぶ時間も大切にしたいですよね。
プログラミング教育は決して難しいものではありません。
まずは今日から、お子さんと一緒に「人間ロボットゲーム」から始めてみませんか?
プログラミング的思考という未来につながる思考力を、家庭時間の中で育てていきましょう。
ここまで読んでくださったママさんパパさんに、充実の時間が訪れますように。
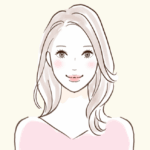
「もっと早く始めればよかった!」と後悔しないためにも、少しでも気になったらプログラミング教育を始めてみてくださいね。お子さんのミライのスキルの第一歩です。