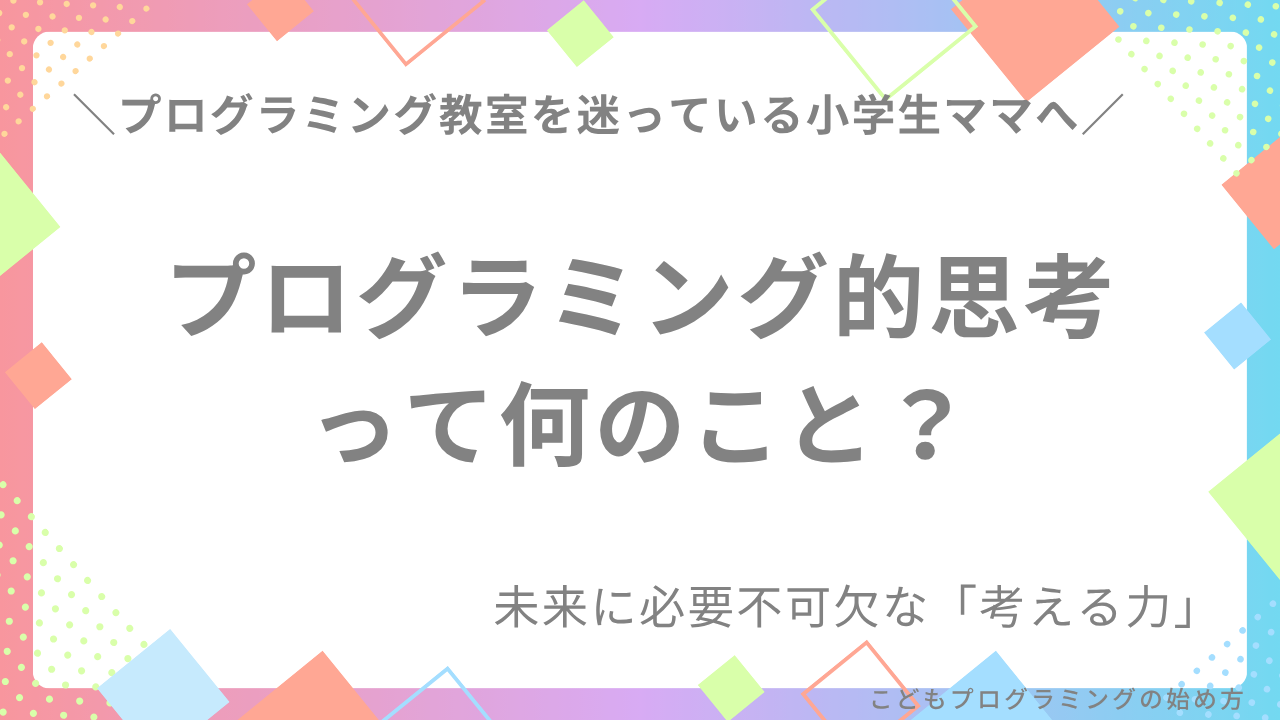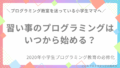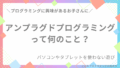「プログラミング的思考って、正直何のことだかさっぱり分からない」
「プログラマーにならないのに、本当に必要なの?」
「うちの子にどう役立つのか具体的にイメージできない」
そんな疑問を持つママも多いのではないでしょうか。
でも、ちょっと待ってください。
プログラミング的思考は、プログラマーだけのものではありません。
実は、プログラミング的思考は私たちの日常生活の中で既に使っています。
とても身近な「考える力」なんですよ。
この記事では、プログラミング的思考の本当の価値と、それが子どもたちの未来にどう役立つのかを、ママの視点から分かりやすく解説します。
この記事を書いた人
プログラミング的思考をわかりやすく
わかりやすくいうと、プログラミング的思考とは、「最適な方法で問題を解決するためにはどうすべきか試行錯誤する」ことです。
プログラミング的思考は「ゴールに到達するまでの動きを細かく分解し」「効率的に動くルートを考え」「試行錯誤しながら最適なルートを導き出す」考える力のことなのです。
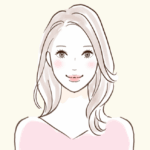
プログラミング的思考は難しいコードを書くためだけの思考法ではないのです。
プログラミング的思考の5つの要素
プログラミング的思考は、5つの要素に分けられます。
1. 分解:物事をこまかくわけて考える
大きな問題を小さな部分に分けて、一つずつ解決していく力です。
2. 一般化:似ている部分や関係性を見つける
物事の似ている部分や関係性などからまとまりを見つけて考える力です。
3. 組み合わせ:さまざまな方法を組み合わせる
効果的な解決策を作り出すために、複数の要素を組み合わせる力です。
4. 抽象化:本質を見つけて大事なことだけに絞る
本質を見極めて、大事なことだけに焦点を当てて考える力です。
5. シミュレーション:頭の中で手順を予測する
頭の中で手順を予測し、結果を想像する能力です。
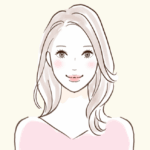
難しく見えるかもしれませんが、これらを説明する代表的な例が料理です。
実は身近にある!日常生活のプログラミング的思考
料理でのプログラミング的思考
カレーを作る例を考えてみましょう。
「カレーを作る」というゴールのために、手順を考えるとこうなりますよね。
・材料を切る
・フライパンで炒める
・水を沸騰させて煮込む
・カレールーを入れる
・味見をしながら味を調整する
このように手順を分解することで、まだ料理をしたことがない子どもでも理解できるようになりますよね。
目的地への移動でのプログラミング的思考
例えば、「○○目的地に早く到達したい」というゴールがあったとします。
それを実現するためには「どのような経路をどのように移動するのがベストか」を考えて、「もっと早く到着するために改善できるところはないか?」などを考えることが、プログラミング的思考といえますね。
お片付けでのプログラミング的思考
子どもに「お部屋をきれいにしなさい」と言っても、子供にうまく伝わらない時ってありますよね。
そういう場合には、手順を分解して子供に教えてあげると、子供も行動しやすくなります。
- おもちゃを種類別に分ける
- 本は本棚に戻す
- 洋服は洗濯かごに入れる
- 床にあるものを全部片付ける
こうすれば、子供も「何をすればいいか」が明確になりますよね。
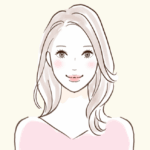
こう考えると、日常生活でも役に立っている思考法だと思えますよね。
「論理的思考」との違いは何?
「論理的思考とプログラミング的思考はどう違うの?」と感じているママもいるのではないでしょうか。
論理的思考とは、物事を筋道立てて考える基本的な思考力です。
一方、プログラミング的思考は、目的を達成するために必要な行動を細かく分解し、順序立てて実行するという思考法です。
単にゴールを達成するだけでなく、「効率化」「仕組み化」「自動化」といった視点を加えることが特徴です。
つまり、論理的思考をベースにしながら、より実践的で効率的な問題解決を目指すのがプログラミング的思考なのです。
家庭でできる!プログラミング的思考の育て方
1. 日常の「なぜ?」「どうして?」を大切にする
子どもが「なんで?」と聞いてきたときは、一緒に順序立てて考える絶好のチャンスです。
- 「どうしてそうなったと思う?」
- 「どうすれば解決できるかな?」
- 「他にも方法があるかな?」
2. 家事を一緒に「手順」で考える
「1日の中でやりたいことをリストアップして、実行する順番を決める」ことから始めましょう。
朝の準備を例にして考えてみましょう。
- 起きる時間を決める
- 着替える
- 顔を洗う
- 歯磨きをする
- 朝ごはんを食べる
- 持ち物を確認する
3. ゲーム感覚で楽しく学ぶ
- 宝探しゲーム:「ヒントを順番に解いて宝物を見つけよう」ゲームをする
- お料理のお手伝い:「材料を順番に入れる理由」を一緒に考える
- 積み木やパズル:「どう組み合わせると目的の形になるか」を試行錯誤する
4. 失敗を歓迎する環境作り
うまくいかなかったり、失敗したりすることも、もちろんあります。
失敗を責めるのではなく、試行錯誤と改善をすることが大切です。
問題点を見つけ、手順を改善していきましょう。
- 「どこで困ったかな?」
- 「次はどうしてみる?」
- 「別の方法もあるかもしれないね」
プログラミング的思考が身についた場合の変化の例
学習面での変化
- 宿題を計画的に進められるようになる
- 難しい問題を小さく分けて考えられる
- 「なぜ?」と理由を考える習慣がつく
生活面での変化
- 時間の使い方が上手になる
- 友達との問題も冷静に解決できる
- 新しいことにもチャレンジしやすくなる
将来への影響
- 問題解決能力の向上
- 創造的な思考力の育成
- 論理的なコミュニケーション能力
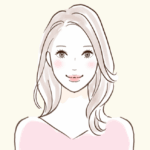
プログラミング的思考を身につけることは、お子さんの自主性を育てることにもつながるでしょう。
よくある誤解
誤解1:「プログラマーになるための勉強」
× プログラミング的思考 = プログラマー育成
◎ プログラミング的思考 = あらゆる職業で使える問題解決力
誤解2:「コンピューターが必要」
× パソコンがないと学べない
◎ 日常生活のあらゆる場面で育てられる
誤解3:「理系の子だけに必要」
× 数学や理科が得意な子向け
◎ 文系・理系問わず、すべての子に有益
注意点:無理強いは逆効果
避けるべき行動
- 「論理的に考えなさい!」と叱る
- 完璧な答えを求める
- 大人の価値観を押し付ける
効果的なアプローチ
- 子どもの「なぜ?」を大切にする
- 試行錯誤を認める
- 失敗から学ぶ経験を提供
まとめ:未来への最高のプレゼント
プログラミング的思考は、決して難しいものではありません。
私たちが日常的に使っている「考える力」を、少し意識してみるだけなのです。
家庭でできること
- 「なぜ?」「どうして?」の対話を増やす
- 家事や遊びを「手順」で一緒に考える
- 失敗を恐れず試行錯誤する環境を作る
- 子どもの「気づき」を褒めてあげる
これからの未来を生きる子どもたちにとって、プログラミング的思考は読み書き計算と同じくらい基礎的な力です。
普段の生活の中で、お子さんと一緒に「どうすればいいかな?」「なぜそうなるのかな?」と考える時間を大切にしてみてください。
今日から、親子で一緒に「考える力」を育てていきませんか?
プログラミング的思考を身につけたお子さんは、きっと「自分で考えて、自分で解決できる」姿になってくれるでしょう。
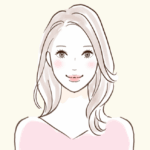
「もっと早く始めればよかった!」と後悔しないためにも、少しでも気になったらプログラミング教育を始めてみてくださいね。お子さんのミライのスキルの第一歩です。