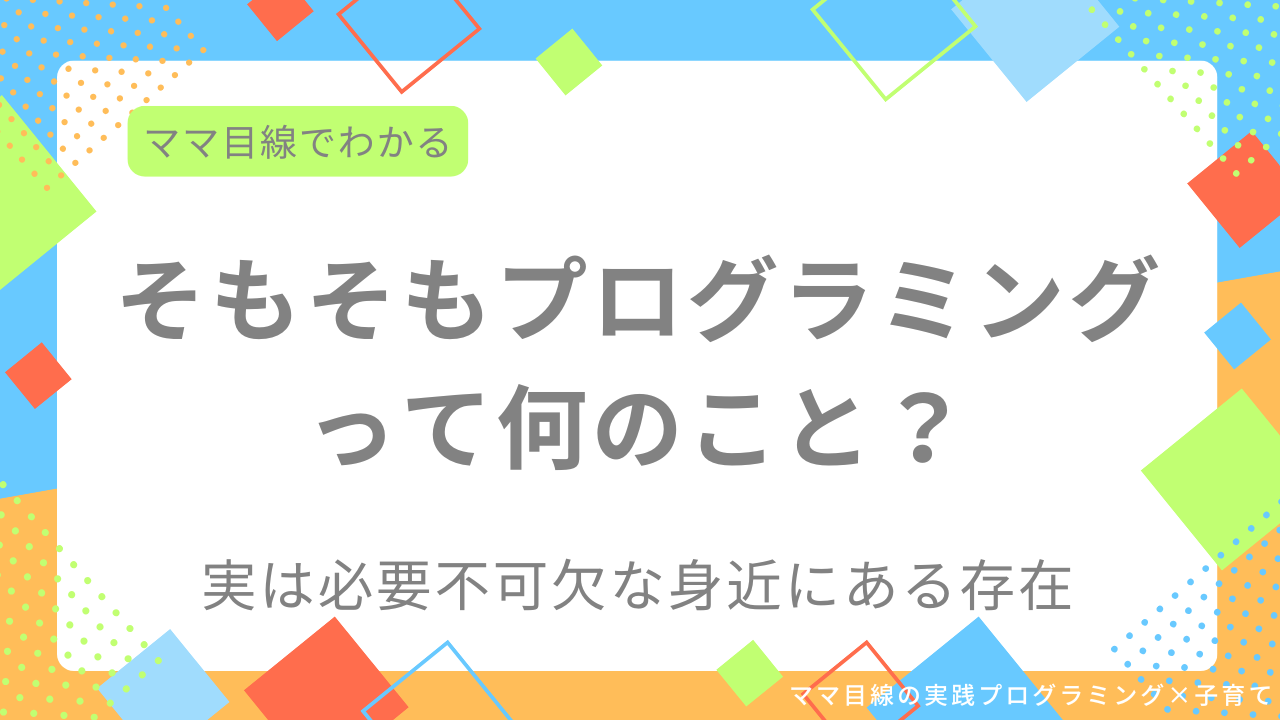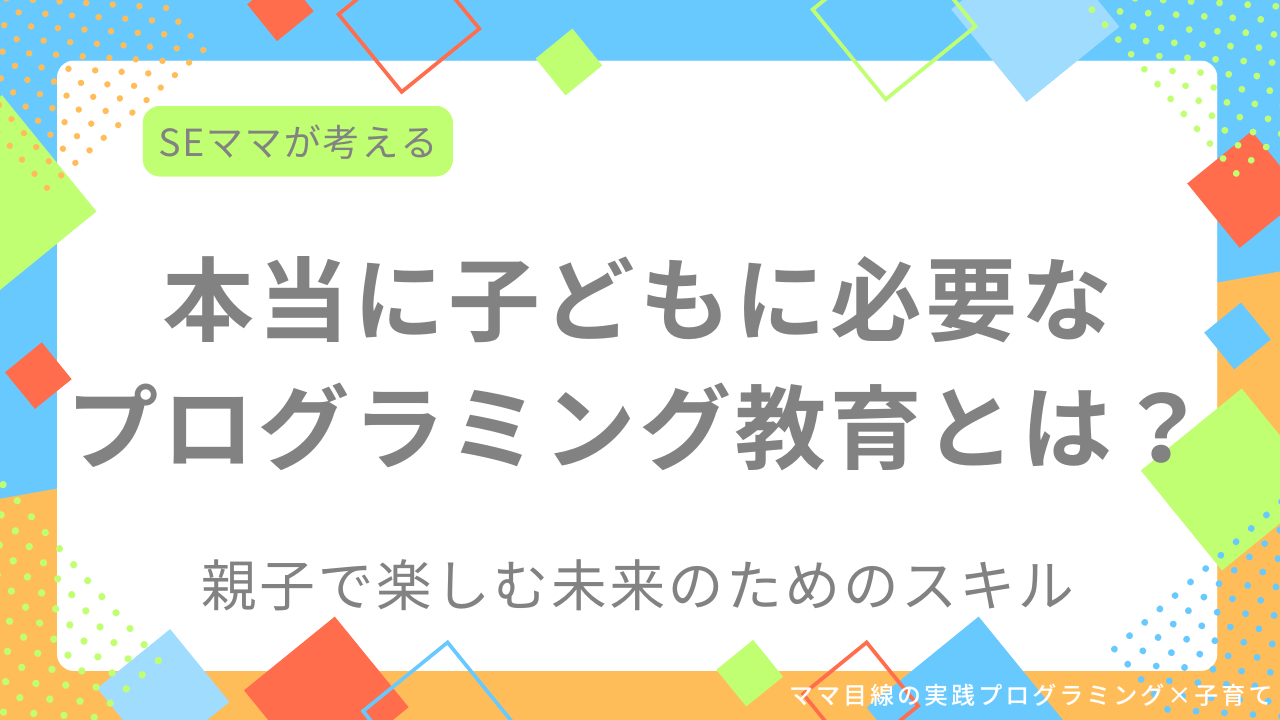「え?うちの子がプログラミング?」
「難しそうで私には教えられない…」
こんな不安を感じている保護者の方、実はあなただけではありません。
でも、安心してください。
小学校のプログラミング教育は、あなたが想像しているものとは大きく違うかもしれません。
そもそも、なぜプログラミングが必修化されたの?
実は「コーディング」を覚えることが目的ではない!
多くの保護者が誤解していることの一つが、「小学校でプログラミング言語を覚えさせるんでしょ?」という認識です。
実際は全く違います。
文部科学省が目指しているのは「プログラミング的思考」の育成なんです。
プログラミング的思考というのは、このような考える力のことを目指しています。
- 物事を順序立てて考える力
- 問題を分解して整理する力
- 論理的に筋道を立てて考える力
つまり、日常生活でも使える「考える力」を育てることが本当の目的なのです。
デジタル社会を生きる子どもたちのために
令和の時代、お子さんが大人になる頃には、今よりもさらにデジタル化が進んでいることは間違いありません。
その時に必要なのは、コンピュータがどのように動いているかを理解し、上手に活用できる力なのです。
そのために、小学校からの教育が必修化されました。
実際の授業って、どんなことをしているの?
「プログラミング」という教科はない!
驚かれるかもしれませんが、時間割に「プログラミング」という教科は存在しません。
- 算数の時間:図形の性質を調べるために、コンピュータで正多角形を描く
- 理科の時間:電気の働きを学ぶために、LEDを点滅させるプログラムを作る
- 総合的な学習の時間:地域の魅力を伝える簡単なゲームを作る
このように、既存の教科の中で自然に取り入れられているのです。
使う道具も子どもに優しい
「難しいプログラミング言語を覚えるの?」という心配も不要です。
小学校では、ビジュアルプログラミングといったアイコンやマークを並べて操作するプログラミングツールが使われています。
- Scratch(スクラッチ):ブロックを組み合わせるだけでプログラムが作れる
- viscuit(ビスケット):絵を描いて動かすことができる
- ロボットプログラミング:実際に動くロボットを操作できる
文字を打つ必要がほとんどないので、低学年からでも楽しく学べます。
保護者の「よくある勘違い」を解消!
勘違い①「家でもパソコンを買わなきゃ」
→ 今すぐには必要ありません。
子供が興味を持った時に考えれば大丈夫です。
勘違い②「私がプログラミングを覚えて教えなきゃ」
→ 本格的である必要はありません。
むしろお子さんと一緒に「どうしてそう考えたの?」と対話することの方が大切です。
勘違い③「理系の子じゃないとついていけない」
→ 文系・理系は関係ありません。
「順番に考える」ことは、作文を書く時や料理を作る時にも使う、とても身近な思考法なのです。
勘違い④「将来プログラマーにならせようとしている」
→ 職業訓練ではありません。
どんな職業に就いても役立つ「未来のための考える力」を育てることが目標です。
子供の様子で「成長のサイン」をチェック!
プログラミング学習で身についた力は、こんなところに現れてくるかもしれません。
- 料理の手伝いで:「最初にお米を研いで、次に水を入れて…」と順序立てて説明できる
- 片付けの時:「どこから片付けると効率的かな?」と考えるようになる
- 友達とのトラブルで:「なぜこうなったのか」を順序立てて説明できる
- 宿題に取り組む時:大きな課題を小さく分けて取り組むようになる
これらは全て「プログラミング的思考」が育っている証拠なのです。
家庭でできる「プログラミング的思考」の育て方
特別なことは不要!日常会話で十分
- 「どうして?」を大切に:お子さんの行動や判断に「どうしてそう思ったの?」と聞いてみる
- 一緒に計画を立てる:「明日の遠足の準備、何から始める?」と順序を考える機会を作る
- 失敗を責めない:「うまくいかなかった時、次はどうする?」と改善点を一緒に考える
「○○したら、○○になる」を意識する
これはプログラミングの基本的な考え方にも通じています。
- 「雨が降ったら、傘を持っていく」
- 「宿題を忘れたら、先生に謝る」
- 「早起きしたら、朝ごはんをゆっくり食べられる」
こんな当たり前の「もしも→そうしたら」の関係を意識して話すだけでも、論理的思考力を育てることにつながります。
「うちの子は大丈夫かな?」と不安な保護者の方へ
「苦手」があっても問題なし
- パソコン操作が苦手→友達と教え合いながら覚えていくことで十分です。
- 論理的思考が苦手→ゲーム感覚で楽しく始めていきましょう。
- 集中力が続かない→短時間で達成感を味わえる活動が中心で、小さな成功体験を積み重ねていきましょう。
まとめ:プログラミング教育は「生きる力」を育てる
小学校のプログラミング教育は、決して「難しいコンピュータの勉強」ではありません。
お子さんが将来どんな道に進んでも役立つ「考える力」「問題解決力」「創造力」を育てる、とても実用的な学習なのです。
ママやパパがプログラミングを勉強して教えてあげなきゃ!と心配に思う必要はありません。
お子さんが学校で学んだことを「すごいね!」「どうやって考えたの?」と興味を持って聞いてあげること。
それだけで十分なサポートになります。
令和の時代を生きる子どもたちにとって、プログラミング的思考は読み書き計算と同じくらい基礎的な力。
お子さんの新しい可能性を信じて、温かく見守っていきましょう。